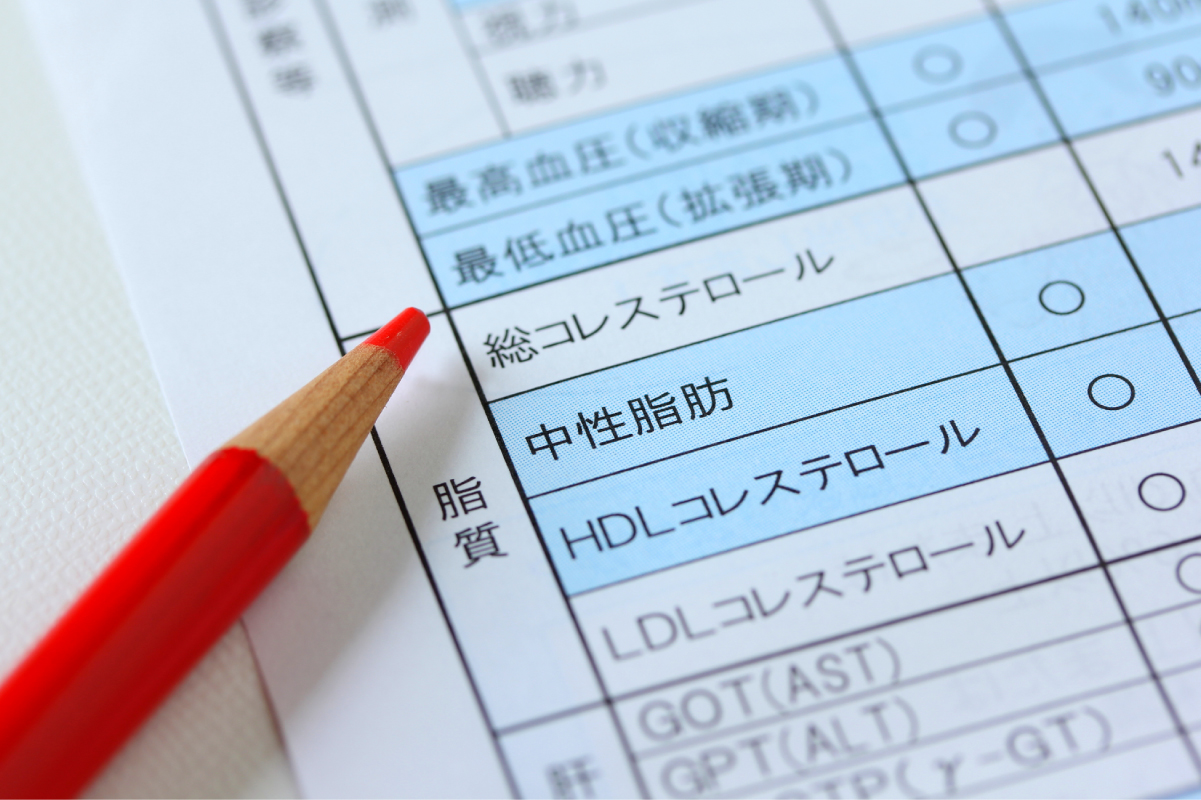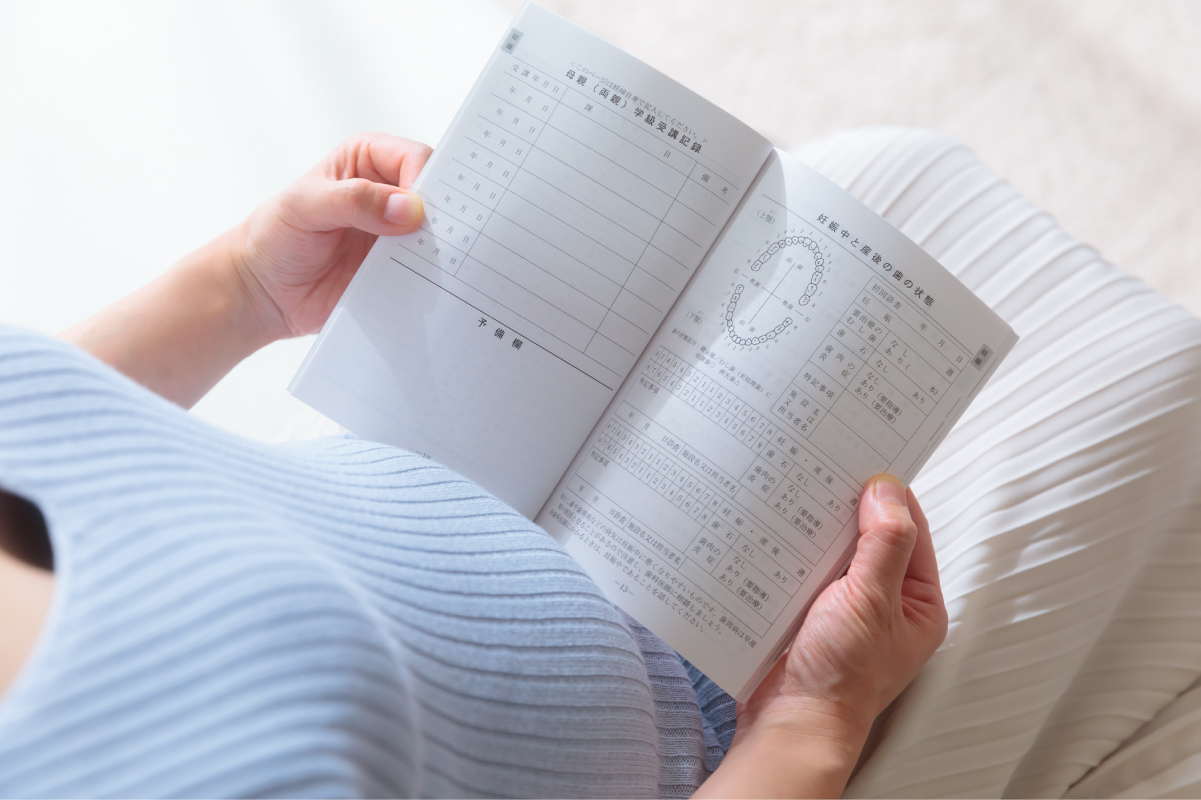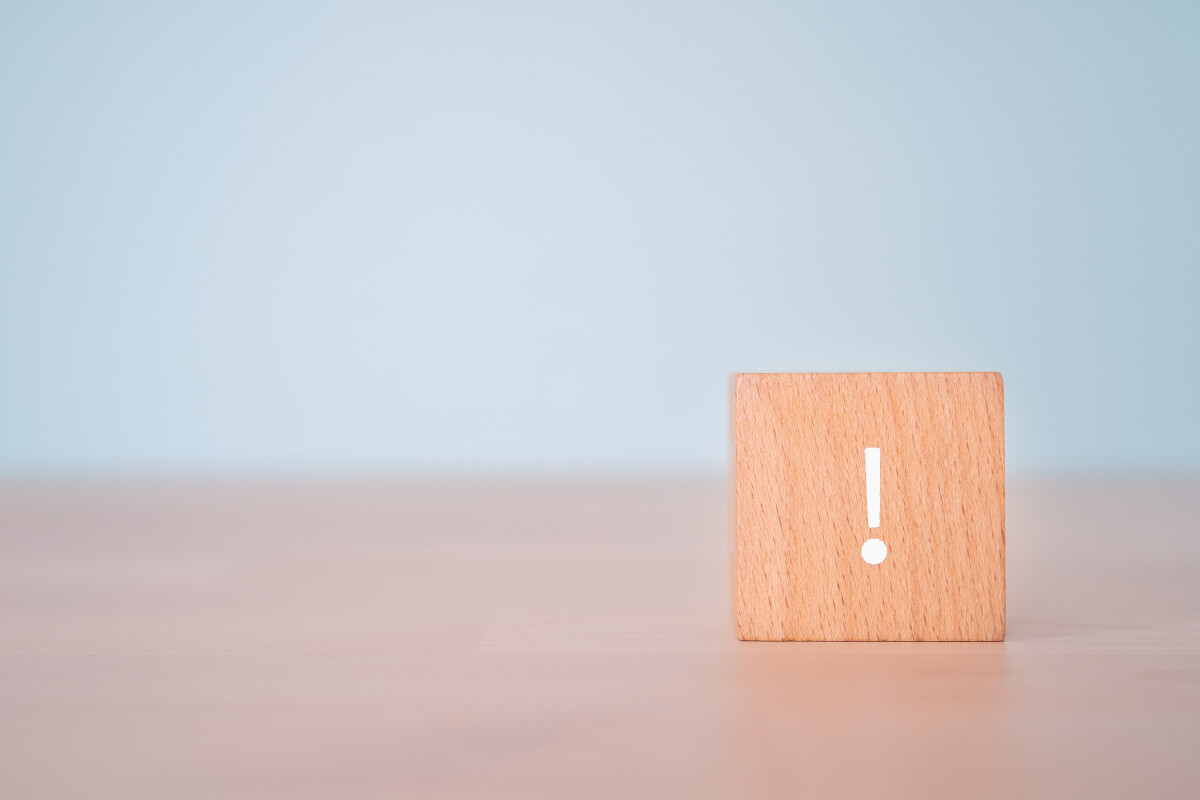- コラム -COLUMN
健康な歯と歯ぐきをまもるために…。
歯の健康に関するコラム記事を
ご紹介しています。
2025/11/17
子どもの虫歯は減っているのに
歯周病が増えている理由|
原因と予防法を解説

親になると、自分の歯を大切にするだけでなく、子どもの歯やお口の健康を守る責任も生まれます。赤ちゃんは、離乳食を開始する6か月頃から徐々に乳歯が生えるようになります。また、6歳ごろになると永久歯への生え変わりも始まる年齢です。歯の萌出に喜びを感じ、虫歯(むし歯)にならないようにと、歯ブラシや歯磨きシートなどを使ったケアを始める方も多いのではないでしょうか。
しかし、「子どもの歯周病」にまで意識が向いている保護者はまだ少ないかもしれません。実は、乳歯や生えたばかりの永久歯も、歯周病になるリスクがあります。歯肉が覆いかぶさり磨きにくかったり、仕上げ磨きが不十分だったり、甘いものの摂りすぎや栄養バランスが乱れたりする時に、歯茎(歯ぐき)に炎症が起きやすくなるためです。
今回は、そんな子どものお口のトラブルである「虫歯」と「歯周病」について解説します。虫歯対策の意識はしていても、子どもの歯周病について考えたことがないという人は多いかもしれません。お子さまの歯茎が腫れている・赤い、出血しやすい、口臭が気になるといったサインがある際は、早めの対処が大切です。小さな頃からの正しい歯磨き習慣は、一生の財産になります。子どもの歯周病が気になる人や、歯磨き習慣を見直したい保護者の方は、ぜひ本記事を今後のケアの参考にしてみてください。
小児の虫歯有病率は激減している!
その理由とは?
子どものお口のトラブルというと「虫歯」が一番に思い浮かぶのではないでしょうか。実際に、1980~1990年代には、幼稚園~高等学校の子どもたちの虫歯有病率は約90%と高く、ほとんどの子どもに虫歯があったことが過去の統計調査からわかっています。しかし、令和5年度の学校保健統計調査では、幼稚園22.55%、小学校34.81%、中学校27.95%、高等学校36.38%という結果となり、大幅に改善が見られました。
なぜ若年性の虫歯が減ったのか?この背景には、主に以下のような予防歯科の普及と意識の変化が関係していると考えられます。
- 乳幼児健診での歯科検査・フッ素塗布
- 学校でのブラッシング指導や歯みがき教育
- フッ素入り歯磨き粉の普及と、ケア用品の進化
このように、虫歯のリスクは減少傾向にありますが、完全になくなったわけではありません。虫歯を防ぐには、日々の正しいケアの継続と定期的な歯科受診を行っていくことが重要です。
子どもの歯周病が増加しているのは
なぜ?
虫歯の子どもが減っているということは、子どものお口の心配事も減っているということでしょうか?実は、そうとも言い切れません。虫歯が減っている一方で、近年、歯周病の子どもが増えてきています。子どもが歯周病?と疑問に思う方も多いかもしれませんが、子どもも大人と同様に歯周病になります。
歯周病は、歯垢(プラーク)や歯石などに潜む細菌の繁殖が起こり、それが原因で歯茎が炎症を起こして発症する病気です。放置して症状が進行すると、歯茎だけでなく歯槽骨と呼ばれる歯を支える骨にまで侵襲が及びます。歯槽骨が溶けると歯がぐらつき、抜け落ちて歯を失う可能性さえあるため放っておくのは危険です。
歯周病の子どもが増えている理由として、以下の影響が考えられます。
・食事や食生活の変化
やわらかくて糖分が多い食事が増えあまり嚙まなくてもよい食事が増加しています。このような食事は歯に汚れが残りやすいうえ、よく噛まない食事で唾液の分泌が減少するため、唾液の「自浄作用」の力が弱まり、口腔内の細菌が繁殖しやすくなります。
・口呼吸
アレルギー性鼻炎や姿勢の悪化、やわらかい食品が増え硬いものを食べることが減ったことによる口周りの筋力の低下などにより、無意識のうちに口呼吸をする子どもが増加しています。口の中が乾燥し、唾液による抗菌作用が低下する原因です。
・ライフスタイルの変化と生活リズムの乱れ
ゲームやスマホの使用、夜更かしなどにより、睡眠のための時間が不足したり、栄養の偏りが起きたりすることで免疫力の低下を招きます。歯周病は細菌感染によって起こるため、免疫力が下がると感染しやすくなるのです。
歯周病対策には「生活習慣の見直し」がカギとなります。
子どもであっても、毎日の丁寧なブラッシングや食習慣の見直し、鼻呼吸の習慣づけなど、お口の中が不潔にならないよう日常的な予防がとても大切です。虫歯だけでなく、歯茎の状態にもきちんと注意を払い、気になる症状があれば早めに歯医者での診療を受けましょう。
また、女子の場合、思春期を迎える小学校高学年~中学生頃に女性ホルモンの分泌が活発になります。この女性ホルモンは、特定の歯周病菌を増殖させる作用があることが分かっています。そのため、ホルモンバランスが大きく変動する思春期は、特に注意が必要であることを知っておくとよいでしょう。
虫歯がないからと油断は禁物!
子どもに必要な歯周病対策
子どもの虫歯の本数や有病率が減っているからと言って、安心はできません。虫歯羅患率は減少していますが、生活習慣の変化により歯周病の子どもは増加しています。歯周病は初期段階では自覚症状が少ないため、「虫歯がない=健康なお口」と思い込んでしまいがちです。そのため、以下のような予防方法が重要です。
・毎日の歯磨き習慣の定着
食後や就寝前にしっかり歯磨きを行い、歯周ポケットまで歯垢の磨き残しがないような習慣を身につけさせましょう。上手に磨けない小さな子どもには、親の仕上げ磨きや磨き残しの確認が欠かせません。
・口呼吸の改善
口呼吸はお口の乾燥を招き、唾液による自浄作用を低下させて歯周病リスクを高めます。普段から「お口を閉じようね」と声かけをし、鼻呼吸を意識させましょう。
・口腔ケアグッズを活用
歯周病予防ができる歯磨き剤や、便利な小児用口腔ケアアイテムを活用しましょう。ドラッグストアやネットでも手軽に購入ができます。うがいができない子どもでも使える歯磨きジェル、乳歯にも使える子ども用サイズのデンタルフロスや歯間ブラシなど、製品の種類も充実しています。
上記のような習慣やアイテムを取り入れ、適切な口腔ケア習慣を定着させましょう。また、定期的に歯科医院を受診し、歯や歯肉のチェック、セルフケアでは落としきれない歯垢・歯石を除去してもらうクリーニングを受けることも大切です。口腔トラブルの早期の発見にもつながります。
虫歯がなくても、
歯茎の健康チェックを
「虫歯がない=安心」という考え方は見直しが必要です。最近では、お口の健康意識も昔に比べて高まっているため、これからは「虫歯と歯周病、どちらも予防するケア」がという考え方を持つとよいでしょう。
特に、子どもの多くは自分でお口の不調を訴えることが難しく、歯肉炎や軽度歯周炎などの初期の歯周病の特徴に気づきにくいこともあります。歯茎の腫れや、仕上げ磨きのときに出血するケースは注意が必要です。子どもの時期の口腔ケアは親のサポートが不可欠なため、異常やトラブルに気づけるようにしておきましょう。
小児歯科では、虫歯だけでなく歯周病や歯茎の状態のチェックも行うことができます。お子さまのお口の中が気になるときは、迷わず歯科医院・クリニックに相談してみましょう。歯科医や歯科衛生士などの検診による専門的な視点からアドバイスをもらい、必要に応じて早めに治療を受けることが、将来のトラブル予防につながります。
子どものお口の健康は、毎日のケアと早期発見がカギ。今からでも遅くありません。当記事ご紹介の情報を元に、歯茎の健康にも目を向け、家族で歯周病予防を意識した予防歯科の習慣づくりを始めましょう。