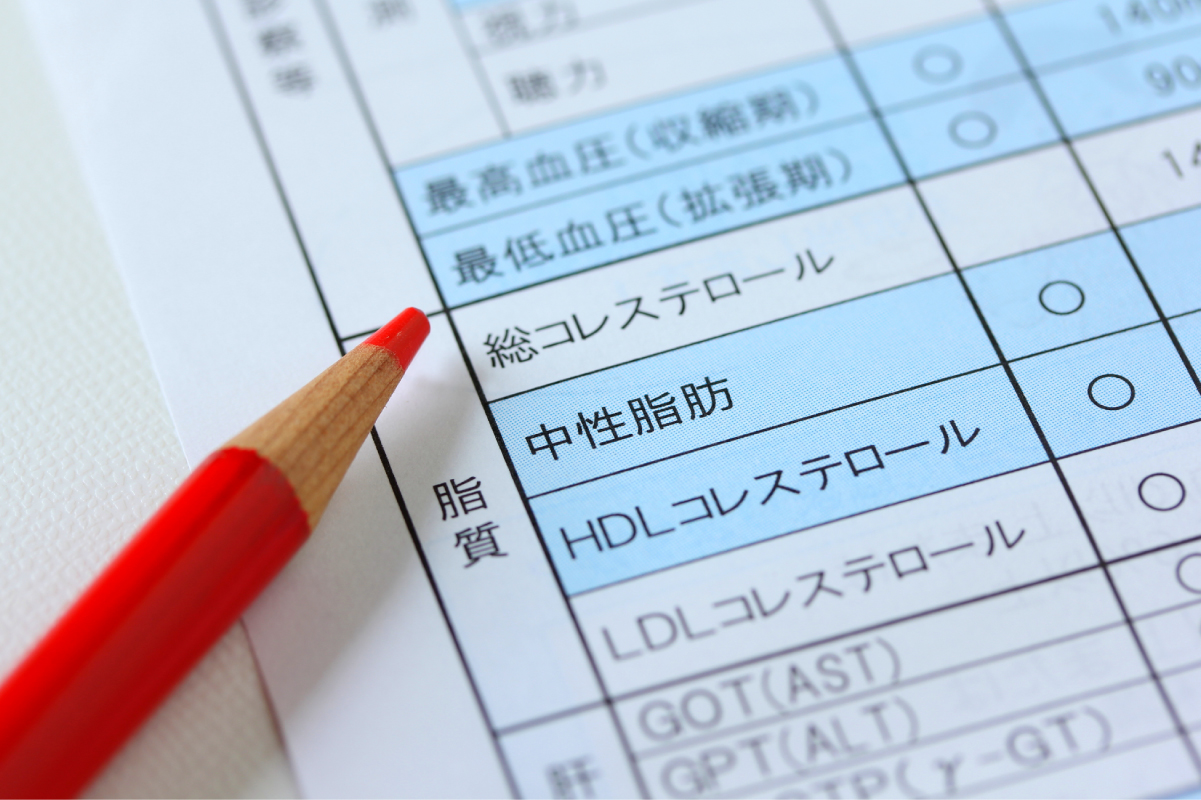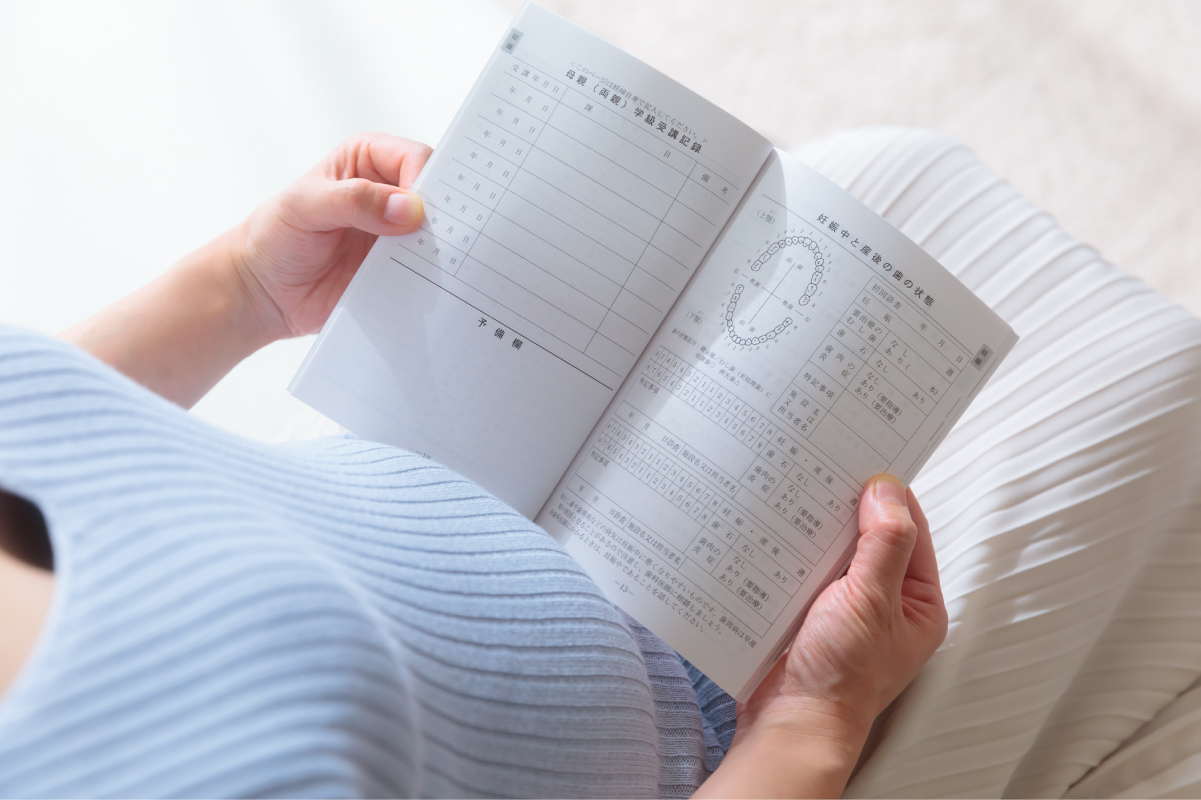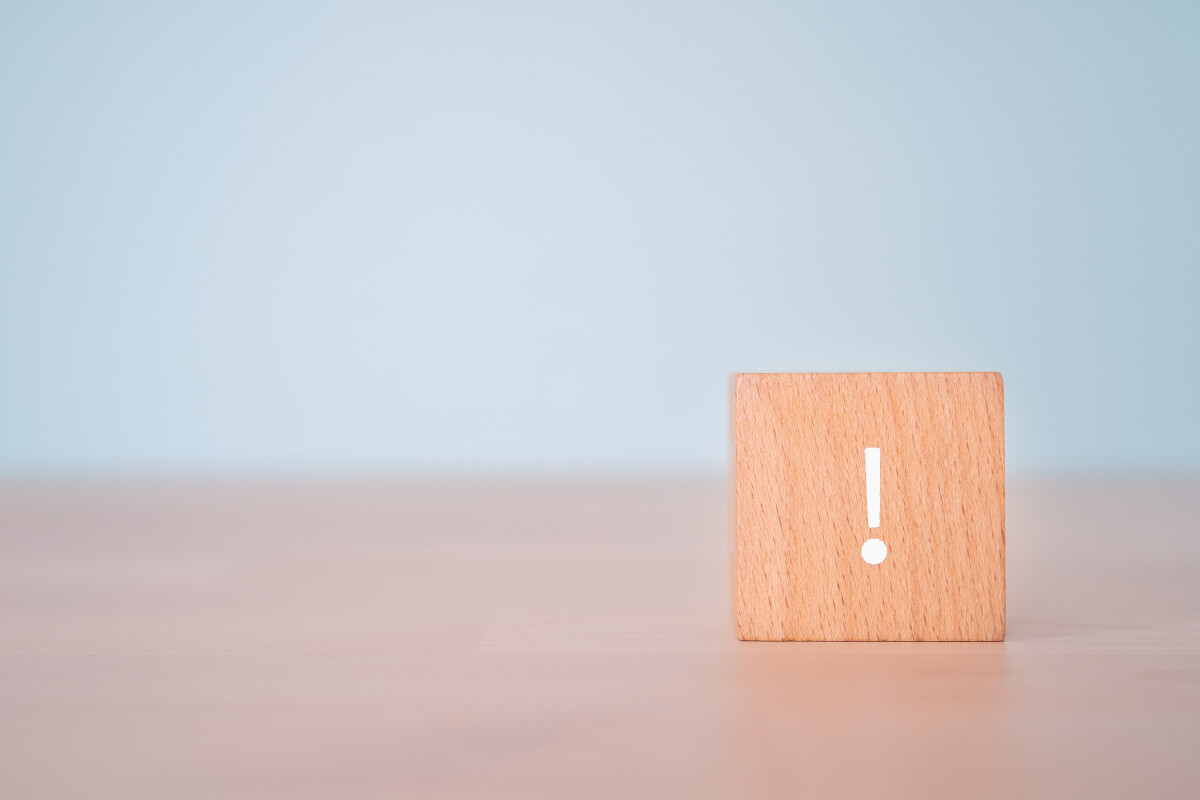- コラム -COLUMN
健康な歯と歯ぐきをまもるために…。
歯の健康に関するコラム記事を
ご紹介しています。
最終更新日:
歯周病になりやすい人の生活習慣は?歯磨き以外の注意点や予防法を解説

歯周病は「国民病」と称されるほど日本人の罹患割合が高く、30代で3割、40代になると半数の人が進行した歯周病であるとされています。炎症が軽い段階の歯肉炎まで含めれば、40代の約8割が歯周病です。歯周病は、罹患者も多く認知度も高い病気のひとつですが、「口の中だけの問題」と侮るのは危険です。歯周病は、歯を失う原因のトップであり、心筋梗塞や脳梗塞・糖尿病などの命に強く関わる病気の引き金になることも報告されています。
そんな全身疾患のリスクもある非常に恐ろしい歯周病ですが、歯磨きをしないことだけが歯周病になる原因ではありません。実は日常生活を送る際にも、歯周病になるリスクを高める行為があるのです。本記事では、歯周病になりやすい人の特徴や生活習慣などのリスクについて、詳しく解説していきます。予防のための改善ポイントについても紹介しますので、歯周病や歯肉炎の予防を意識したい方などはぜひ参考にしてください。
歯周病になりやすい人は
何気ない生活習慣がリスクに
歯周病は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)や歯石により、歯茎(歯ぐき)が感染し炎症を起こす病気です。初期には痛みがないことが多く、気づかないまま進行してしまうケースも少なくありません。徐々に歯茎が赤く腫れ、出血やねばつき、口臭がするといった症状があらわれます。重症になれば、歯を支える骨が溶けて歯のぐらつきや喪失のリスクもあるため、早期に適切な対応をとる必要があります。
磨き残した歯垢を除去できれば歯周病への感染リスクは抑えられますが、それだけが原因というわけでもありません。歯周病になる理由として、大きく分けて以下3つの要因があります。
【歯周病を引き起こす3つのリスク】
-
口腔内の要因
歯垢・歯並び・歯みがき・嚙み合わせ・歯ぎしり・食いしばり・口呼吸など -
環境の要因
ストレス・喫煙・飲酒・食生活・不規則な生活など -
宿主の要因
年齢・人種・持病・遺伝・肥満・免疫力の低下など
歯周病を引き起こしやすいリスク要因が重複すると、歯周病発症の危険性が高まります。ここからもわかるように、ただ丁寧な歯磨きをしていれば歯周病にならないというわけではありません。普段気にもとめないような何気ない毎日の生活習慣や癖が、歯周病のリスクを高めている可能性があります。
意識せずに行う習慣や癖は、特に変えることが難しく、改善に時間がかかるでしょう。例えば、ストレスの蓄積や睡眠不足、食生活の乱れ、喫煙などもその一因です。まずは、できることから始めて、「自分の生活の中にリスクが潜んでいるかもしれない」と意識することが、歯周病対策への第一歩となります。
また、歯茎の腫れや出血、口臭などの歯周病かもしれない症状や悩みがあれば、決して放置せずに早めに歯医者に相談することをおすすめします。
自覚症状がないまま進行するケースも多いため、「痛くないから大丈夫」と思わず、定期的な歯科検診でのチェックも重要です。
歯周病の予防は食生活・喫煙・ストレスに
気をつけよう!
歯周病を防ぐために気をつけたい生活習慣が、食生活・喫煙・ストレスの3つです。
・食生活の見直し
歯周病の予防において、食生活で気をつけたいのは、時間に関係なく長時間かけてだらだらと食べることです。間食が多いと、食べ物に含まれる糖分をエサとして口の中の細菌が繁殖し、歯周病の原因となる歯垢が作られます。また、食事中はよく噛むことを心掛けましょう。柔らかい食事ばかりで噛む回数が少ないと、唾液の分泌が減ってしまいます。唾液には自浄作用があり、お口の中をきれいにしてくれる力があるためとても大切です。唾液不足は口腔内の衛生状態を悪化させる原因になります。就寝の間は、この唾液は分泌しにくく口腔内が乾燥しやすいため、菌が増殖しやすい環境です。寝る直前の食事や間食も避けた方がよいでしょう。
・喫煙習慣
喫煙は、歯周病の最大のリスク因子の一つ。タバコの煙を口の中の粘膜などから吸収し、一酸化炭素やニコチンにより血管が収縮し血流が悪くなるなどして血行を損ない、歯周組織へのダメージにつながると言われています。また、歯にタバコのヤニが付着することで、ざらついた歯に汚れや菌が付着しやすい状態を起こします。喫煙者にとっては大変かもしれませんが、禁煙で歯周病リスクは下げられるため、歯周病で大切な歯を失わないためにもタバコは早めに止めるのが一番です。タバコは体にも悪いため、健康のためにも禁煙や減量を検討しましょう。
・ストレスの影響
ストレスも歯周病と大きな関わりがあります。慢性的なストレスは免疫機能を低下させ、感染症への抵抗力を弱めます。ストレスは交感神経を優位にしますが、これにより唾液の分泌が減って口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなるため、歯周病を引き起こしやすくなります。また、ストレスを感じることで歯ぎしりをするという人も少なくありません。歯ぎしりをすることで歯周病になるわけではありませんが、歯茎が弱まり、歯周病があった場合のリスク因子となります。歯ぎしりで起こる歯茎への負担によって、症状が治りにくい・悪化しやすいなどの影響を与えるため注意が必要です。
口腔ケアにプラスして
生活習慣の改善も大切
お口のケアは、歯周病対策の基本です。まずは、丁寧な歯磨きの習慣を心掛けましょう。歯と歯肉の境目である歯周ポケット部分にたまった歯垢を、しっかりとかき出すように磨くのがポイントです。次に、デンタルフロスや歯間ブラシ、マウスウォッシュを取り入れるなど、口腔ケア用品の見直しにも効果が期待できます。予防歯科の広まりから、近年、さまざまな口腔ケア関連グッズが販売されています。歯ブラシ一つとっても、ヘッドの形やブラシの硬さ、電動のものまで種類はさまざまあるため、自分に合った機能の製品を選択・使用するとよいでしょう。
また、セルフケアでは落としきれない汚れは、定期的に歯科医の検診を受け、診療やクリーニングをしてもらうことも大切です。定期歯科検診を受診することで、歯周病リスクをかなり減らすことができます。必要時には、歯科医師や歯科衛生士からブラッシング指導を受けることもできるため、ご自身の歯磨きを確認したい方は指導を受けるのもよいでしょう。かかりつけの歯科医院ができることで、何かトラブルがあっても相談しやすく、その結果、歯周病やむし歯の早期発見につながり短期間で治療を終えやすいというメリットもあります。
このような毎日の歯磨きに加えて、普段の生活習慣にも目を向けることも重要です。特に食生活・喫煙・ストレスには十分注意が必要です。食事の時間はある程度固定しだらだら食べないようにしたり、寝る前に間食したりするのは控えましょう。また、喫煙者は歯周病になりやすいことがわかっています。禁煙が難しい場合でも、本数を減らすなどできることから始めるとよいでしょう。喫煙がストレス発散になっている人は、運動などの別の発散方法を試す・見つけるのが体の健康にもつながるためおすすめです。
まとめ
歯周病はお口の中の感染症であり、歯磨き不足などといった口の状態だけでなく日々の生活習慣による体の状態によっても起こりやすさは左右されます。そのため、口腔ケアを基本の対策として、合わせて生活習慣を整えることも意識しながら正しい歯周病対策を行いましょう。お口だけでなく全身に悪影響を及ぼす歯周病を予防するためにも、ぜひ本記事の情報をチェックして、日々の歯周病対策にお役立てください。
このように歯科の知識と生活習慣の意識改革を組み合わせることで、歯周病は確実に予防・改善できます。口の健康を守ることは、全身の健康を守る第一歩。今からできることを始めてみましょう。