- 歯科医師インタビュー -INTERVIEW
健康な歯と歯ぐきを守るために、
歯科医師からのメッセージを連載しています。
vol.11
【後編】
歯科医師に聞く!
歯周病・口臭予防の
最新トピックスと今日から
始められる口腔ケア
口臭の原因が歯周病にあるかもしれない

口臭の原因が歯周病にあるかもしれない
りょう歯科クリニック
院長菱川 亮介
口臭の原因が歯周病にあるかもしれないって知っていますか?実は、見えないところで進行する歯周病は、口臭の隠れた原因の一つ。そして、その進行は全身の健康にも影響を与える可能性があります。今回は日本歯周病学会認定医である菱川亮介先生に、歯周病と口臭の関係、そして日常でできる予防策について伺いました。あなたの口腔ケア、今一度見直してみませんか?
また、インタビューの前半部分は下記ページからご覧ください。
【インタビュー前半:】
その口臭、歯周病が原因かも?歯科医師が教えるニオイの正体と毎日の正しいケア習慣
目次
Q5. 口腔内の健康を
語るための栄養や
食生活の影響について
お話しいただけますか?
特に歯周病予防に良いとされる
栄養素や食材があれば
教えてください。

歯周病を予防する習慣、毎日のブラッシングやフロスなどの口腔ケアと同じくらい大切なのが、食生活です。腸内環境と同じで口腔内には歯周病や虫歯などを引き起こす悪玉菌だけでなく、善玉菌や日和見菌(ひよりみきん)といった、良い影響を与えてくれる菌も存在します。善玉菌は口腔内の健康を保ち、虫歯や歯周病、口臭の予防に貢献しています。正しい口腔ケアだけでなくバランスのとれた食生活で善玉菌を増やすことも歯周病の改善や口臭予防につながります。
中でも特に重要なのが、ビタミンC、ビタミンD、オメガ3脂肪酸、ポリフェノール、食物繊維などの栄養素です。 例えば、ビタミンCは歯ぐきのコラーゲンを維持し、出血や炎症を防ぐ働きがあります。ビタミンDは歯ぐきを支える骨(歯槽骨)を守り、免疫力を整える役割があります。さらに青魚やナッツ類に多く含まれるオメガ3脂肪酸には、歯ぐきの炎症を軽くする作用があり、歯周病の進行を抑える効果が期待されています。 緑茶やカカオ、ブルーベリーなどに含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり、細菌の繁殖抑制を中心に働きが期待されています。
また、砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料、酸性の食品を頻繁に摂取することは、細菌の温床となり、歯ぐきの炎症を悪化させる可能性があります。また、喫煙や過度のアルコール摂取も血流を悪化させ、歯周病のリスクを高めることになります。
バランスのとれた栄養、よく噛む習慣、そして炎症を抑える食材の積極的な摂取は、健康な歯ぐきを維持するための大きな力になります。
Q6. 口臭が気になる
患者さんに対して、
歯周病の早期発見のために
日常生活でチェックすべき
ポイントや
初期症状について教えてください
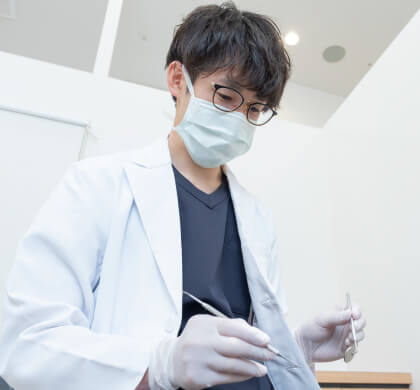
口臭というのは患者さん自身では気づきにくいことが多いため、ご家族やパートナーなど周囲の人から指摘されて初めて自覚されるケースも少なくありません。実際に強烈な臭いがあったとしてもご自身では“ちょっと臭うかな”ぐらいで、自覚が薄い方も多くおられます。周囲の指摘を受け、ガムを噛む、マウスウォッシュを試す、舌苔を落とすなど、策を講じても改善されないようでしたら歯周病を疑ってみるべきかと思います。
具体的な歯周病の初期症状としては歯ぐきの出血や腫れ、色の変化です。健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、炎症があると赤みが現れ、腫れてきます。また、最近歯が長くなったように見えると感じる方は、歯ぐきが後退している可能性があります。これは歯周病によって歯ぐきの組織が破壊されているサインであり、進行性の歯周炎が発症している可能性があります。ご自身でできる口臭のチェックリストもありますので、試してみていただければと思います。
◆今すぐできる自分でわかる口臭チェックリスト:
- 朝起きた時の口の中の状態を確認(乾燥している?唾液が少ない?)
- 舌の色をチェック(白っぽくなっている場合は舌苔が溜まっている)
- 歯ぐきの色をチェック(赤みが強い場合は歯周病のサイン)
- 舌ブラシで舌を清掃してみる(臭いが強い場合は嫌気性菌の可能性
- デンタルフロスで歯間を清掃(出血がある場合は炎症が進んでいる可能性)
気になる点は歯科医院で診てもらいましょう。
Q7. 健康維持の為の
歯周病予防について、
歯科医師として特に推奨する
「すぐに実践できるケアのヒント」
を
教えてください。
歯周病は気づかないうちに進行する病気ですが、既にお話しした「ケア製品を取り入れたセルフケア」「バランスのとれた食事」のほかにも日々のちょっとした習慣の積み重ねで予防することができます。
唾液の分泌を促すことも大切なので、よく噛んで食べることや、食後にキシリトールガムを噛むこと、こまめに水を飲むことといったシンプルな習慣が、口腔内の自浄作用を高めてくれます。特に口の中が乾燥しやすい方は、意識的な水分補給やキシリトールガムの活用なども有効です。日常的に口呼吸ではなく鼻呼吸を意識することなどもお勧めします。また、良質な睡眠やストレスのコントロールも、歯ぐきの健康に重要です。睡眠不足や慢性的なストレスは免疫力を下げ、歯周病の炎症を悪化させることが知られています。毎日の生活の中で、心身のバランスを整える習慣も長期的にはお口の健康につながります。愛好家の方には耳が痛いでしょうが、できれば喫煙、過度なアルコール摂取なども控えられると、なお良いでしょう。
そして何より3〜6ヶ月ごとの定期的な歯科健診を受けることが早期発見・予防の最大のポイントです。定期健診で歯周病の進行を早期発見し、治療につなげましょう。セルフケアでは届かない部分こそ、プロの目でチェックすることが大切です。
Q8. 歯科医の視点から、
歯周病と口臭に関する最新の研究
や
トレンドで注目されているもの
があれば教えてください。
特に、歯ぐきの健康を維持する
ために効果的な方法や
治療に関する
最新情報が
もしあれば知りたいです。
口腔内の善玉菌についてお話ししましたが、善玉菌(プロバイオティクス)を活用した口腔ケアにも注目が集まっています。特定の乳酸菌などを摂取・口腔内に定着させることで、歯周病菌や口臭の原因菌を抑制する働きが期待されています。それからデジタル技術、AIを搭載した口腔内スキャナーなどの進化にも期待しています。今よりも更にミクロな世界まで見えるようになれば、今以上に正確で有効な治療が実現すると思います。
これは昔からある学問ではありますが、東洋医学(漢方)を活用した歯科治療なども注目したいところです。唾液のコントロールや交感神経へのアプローチなど、この分野の歯科への広がりにも期待が寄せられています。歯科で漢方を処方して口臭を改善することも将来できるようになるかもしれません。
Q9. 歯周病や口臭の予防に
関して、他の歯科以外の医療機関
や
健康管理の専門家との連携が
重要だと考えますか?
総合的な健康管理としての
歯周病ケアの重要性について
教えてください。
医科との連携はとても重要です。高齢化社会が進む今、多くの高齢者の方は複数の薬を飲んでいます。医科で処方する薬の中には唾液が少なくなったり、自律神経が乱れたりするような、少なからず口腔内に影響を及ぼす薬などもあります。例えば現在では、お薬手帳やマイナ保険証などを見ることで医科での処方薬を確認できるようになっていますが、医療現場で注射により投与された薬などについては歯科で把握しようがないのが実情です。そういう意味では医師、歯科医師だけでなく薬剤師などとも連携をとっていく必要性は大いにあると思っています。
歯科医師紹介
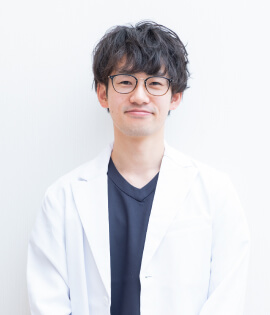
りょう歯科クリニック 院長菱川 亮介
- 日本歯周病学会(認定医)所属
- 日本臨床歯周病学会所属
- 日本口腔インプラント学会所属
岡山大学歯学部卒業(歯科医師免許修得)
岡山大学病院 研修医(複合プログラム)採用
医療法人QOL ファミール歯科 勤務
医療法人山﨑歯科クリニック 勤務
医療法人ゆたか Yes dental office 勤務
医療法人ゆたか We dental clinic 分院長を経て
2025年9月 りょう歯科クリニック 開院

















