- 歯科医師インタビュー -INTERVIEW
健康な歯と歯ぐきを守るために、
歯科医師からのメッセージを連載しています。
vol.11
【前編】
その口臭、歯周病が原因かも?
歯科医師が教えるニオイの
正体と毎日の正しいケア習慣
口臭の原因が歯周病にあるかもしれない

口臭の原因が歯周病にあるかもしれない
りょう歯科クリニック
院長菱川 亮介
口臭の原因が歯周病にあるかもしれないって知っていますか?実は、見えないところで進行する歯周病は、口臭の隠れた原因の一つ。そして、その進行は全身の健康にも影響を与える可能性があります。今回は日本歯周病学会認定医である菱川亮介先生に、歯周病と口臭の関係、そして日常でできる予防策について伺いました。あなたの口腔ケア、今一度見直してみませんか?
Q1. 歯周病と口臭の関係:
なぜ歯周病は口臭を引き起こすの
でしょうか?

ポイント1. 酸素を嫌う“嫌気性細菌”が原因
歯周病と口臭の関係、知っていますか?実は、歯周病は口臭の“隠れた犯人”とも言われています。その原因となるのが、“酸素を嫌う菌”である嫌気性菌です。
例えば、歯周病が進行すると歯ぐきの中に潜む嫌気性菌が増え、その菌がタンパク質を分解する際に発生するガスが、あの“腐った卵”のような臭いを引き起こすのです。歯周病が進行すると歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットが深くなります。歯周ポケットが深ければ深いほど酸素に触れずに済むため嫌気性菌が増えてしまいます。これらの細菌はタンパク質を分解する過程で揮発性硫黄化合物(VSC:硫化水素、メチルメルカプタンなど)を発生させ、これがいわゆる“腐った卵”や“ドブのような臭い”と言われるような口臭の原因となります。特にメチルメルカプタンは、単に臭いが強いだけでなく、歯周組織を破壊する毒性もあることが分かっており、歯周病をさらに悪化させる悪循環を引き起こします。
ポイント2. 出血や膿も原因に
また、歯周病があると歯ぐきから出血や膿(うみ)が出やすくなり、それも口臭の原因となります。歯ぐきから出血がある方や、血の臭いが気になる方も注意が必要です。歯ぐきの健康と口臭は密接に関連しているということです。
少し専門的な名前が出てしまいますが、歯周病菌には、特に危険な「レッドコンプレックス」と呼ばれる菌(Pg菌・Tf菌・Td菌)があります。しかし最近の研究では、これらだけでなく、一見無害に思える菌たちも集合体となって歯周病を進行させることがわかってきています。
つまり、毎日のケアでこれらの菌を含めてしっかりとお口の中をコントロールすることが重要なのです。
Q2. 歯周病による口臭は、
他の原因による口臭と
どのように違うのか、
特徴的な兆候や違いを教えて
ください。
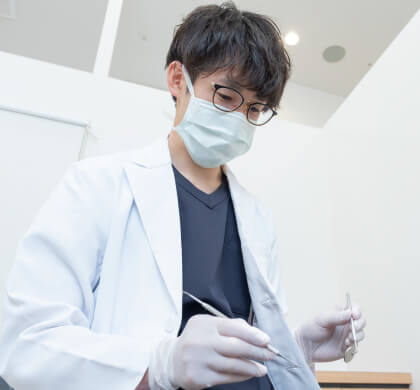
歯周病による口臭は、他の原因による口臭と比べて、いくつかの明確な特徴があります。まず最も大きな違いは、臭いの性質と持続性です。臭いとしては “強烈な腐った卵”のような臭い。そして歯周病による口臭は一時的ではなく慢性的に続くことが特徴です。朝起きたときだけでなく、日中も口臭が気になり、本人よりも周囲の人が気づきやすいという傾向もあります。さらに歯ぐきの出血や腫れ、膿のにじみ出しなどの症状を伴うことも多く、こうした歯周病のサインがある場合は歯周病による口臭の可能性が高いと考えられます。
一方、歯周病以外の原因としては、舌の表面に付着した舌苔(ぜったい、舌の表面に付着する白い汚れ)や、唾液の減少、食べ物の臭い、消化器系の不調なども口臭の原因になります。これらは比較的短時間で改善されることが多く、臭いの質も異なります。たとえば舌苔による口臭は舌ブラシでのケアで改善しやすく、食事由来の臭いは時間とともに自然におさまります。
◆歯周病による口臭の特徴
- 強烈な腐った卵の臭い
- 慢性的に続く(朝だけでなく一日中)
- 歯ぐきの出血や腫れを伴う
◆歯周病以外の口臭の特徴
- 舌苔(ぜったい):白っぽい舌苔が付着しやすい
- 唾液の減少:乾燥した口腔内が臭いの原因に
- 食べ物の臭い:食後に一時的に発生
Q3. 歯周病や口臭予防に特化した
日常的なケア方法や
ルーチンについて、
特に効果的なアプローチがあれば
お教えください
歯周病や口臭を予防するためには、日々のセルフケアが何よりも重要です。基本的には歯ブラシでの正しいブラッシングです。ただ、きちんと磨いても6割7割程度しか汚れは落ちていないというデータもありますから、補助的にフロスや歯間ブラシを使っていくことが大切ですと患者さんにはお伝えしています。特に、夜寝る前にフロスや歯間ブラシを使うことで、歯と歯の間に潜む汚れを取り除き、就寝中の菌の増殖を防ぐことができます。順序としては先にフロスや歯間ブラシをしてから、歯ブラシでブラッシングをしていただくのが効率良く汚れが落ちるとお伝えしています。そしてブラッシングは1回5分以上かけることをお勧めしています。朝晩2回、1日に最低でも10分は歯磨きの時間を取っていただきたいと思います。加えて、舌の表面に付着した舌苔の清掃。舌ブラシや専用のスクレーパーで、舌の奥から手前にやさしくこすって清掃することで、臭いの発生を抑えることができます。
歯ブラシには形、ブラシの大きさ、硬さなど様々な商品が出ています。せっかく時間をかけて磨いているのに、「なんだかスッキリしない...」そんな経験はありませんか?
それ、歯ブラシや歯間ブラシが自分の口に合っていないのかもしれません。一度歯科医院で「自分専用のケアグッズ」を“処方”してもらうのもおすすめです。
Q4. 歯周病や口臭予防に関して、
歯磨き粉やマウスウォッシュの
選択が重要だと思いますが、
特に注目すべき成分や製品の特徴を
教えてください。
「ブクブクうがいだけで歯周病菌を撃退できる」そんなふうに思っていませんか?
実は、歯の表面にこびりついた汚れ(バイオフィルム)はうがいだけでは取り除けません。歯ブラシや歯間ブラシで、しっかり物理的に除去することが大切です。ただ、その際に歯磨き粉やマウスウォッシュを効果的に取り入れるのは良いと思います。どのような成分が含まれているかによって口腔内への効果に大きな差が生まれます。
歯周病の観点から注目したいのは「抗菌」「抗炎症」「歯ぐきの保護」に関わる成分です。たとえば、塩化セチルピリジニウム(CPC)は、細菌の増殖を抑える効果があり、歯周病の原因となるプラークの形成を防ぎます。また、グリチルリチン酸ジカリウムやトラネキサム酸は歯ぐきの腫れや炎症を抑える抗炎症成分として有効です。より効果の高い歯周病対策には、バイオフィルムに浸透して殺菌するIPMP(イソプロピルメチルフェノール)やエッセンシャルオイルが効果的とされています。
口臭に直接アプローチするのであれば亜鉛化合物(硫酸亜鉛など)や二酸化塩素が含まれた製品が推奨されます。これらは口臭の原因となる化合物(VSC)を中和し効果を発揮します。また、緑茶カテキンやラクトフェリンなどのポリフェノール系成分も抗菌・抗酸化作用により口腔内の細菌バランスを整えますし、フェンネル・ペパーミント・シナモンなどハーブオイル系の製品も消臭効果が期待できます。
口臭のケアには、マウスウォッシュの併用も補助的な効果が期待できますが、アルコールを含むものは口腔内の乾燥を招く可能性がありますので、特にドライマウスの傾向がある方にはアルコールフリータイプをお勧めします。刺激も味もマイルドですので取り入れやすいと思います。
ご自身での選択が難しい場合は、先ほどの歯ブラシ同様、歯科医院での相談を通じて自分に最適なケアアイテムを見つけるのがよいでしょう。日々のセルフケアをより効果的にするために、製品選びは“成分重視”がこれからのスタンダードです。
インタビューの後半部分は下記ページからご覧ください。
【インタビュー後半:】
歯科医師に聞く!歯周病・口臭予防の最新トピックスと今日から始められる口腔ケア
歯科医師紹介
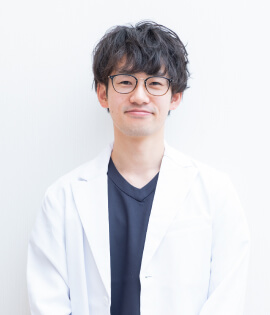
りょう歯科クリニック 院長菱川 亮介
- 日本歯周病学会(認定医)所属
- 日本臨床歯周病学会所属
- 日本口腔インプラント学会所属
岡山大学歯学部卒業(歯科医師免許修得)
岡山大学病院 研修医(複合プログラム)採用
医療法人QOL ファミール歯科 勤務
医療法人山﨑歯科クリニック 勤務
医療法人ゆたか Yes dental office 勤務
医療法人ゆたか We dental clinic 分院長を経て
2025年9月 りょう歯科クリニック 開院

















